2025年5月2日、米国研究製薬工業協会(PhRMA)は、厚労省医薬局医薬品審査管理課に宛てた意見書を自らの日本語ウェブサイト上で公開しました。この意見書は、現在厚労省が検討中の日本版パテントリンケージ制度に対する初期的な見解を述べるものです。
参照:
- 2025.05.02 PhRMA 日本語ウェブサイト News : 厚生労働省提案への初期意見 / Initial Response to MHLW Proposal
厚労省が現在検討しているパテントリンケージ制度への「有識者(専門委員)意見照会制度」導入の構想に対して重大な懸念があることを述べています。
制度検討が進行中であるこの段階で、厚労省に提出した意見をあえて公表したことは、PhRMAが本制度に対して極めて深刻な懸念を抱いていることを示しているといえます。
本記事では、PhRMAの主張の要点と補足的な考察をお伝えいたします。
1.厚労省提案とPhRMAの評価
厚労省は、後発医薬品(ジェネリック)やバイオ後続品(バイオシミラー)の承認審査において、当該申請品が先行品の特許権に抵触するか否かを判断できない場合に、第三者である専門委員に意見照会する制度を提案しています。
参照:

しかし、PhRMAは、この制度が「判断できない場合にのみ利用される」という前提自体には理解を示しつつも、
「日本における先行バイオ医薬品の特許が適切に尊重されること、及び国内の患者が医薬品の安定的な供給を受けられることを確保するかという点については、その制度の有用性に疑問を持っています。すなわち、この点において、提案されている制度は、現行のパテントリンケージ制度が後発医薬品やバイオ後続品の申請について特許権者に十分な通知を提供していないという、先発企業が抱える主要な懸念に対処していません。」
と前置きしたうえで、以下のような懸念を表明しています。
- 厚労省は、後発医薬品やバイオ後続品について先発企業との特許権侵害の有無を判断することは求められておらず、最適任でもない。この判断は、厚労省の技術的専門性や目的を超えるものであり、世界の他のパテントリンケージ制度と同様に、裁判所に委ねられるべき。したがって、厚労省が特許に関する判断について、提案されている専門委員会に照会する必要はない。
- 提案されている制度には、裁判所による判断を遅らせ、承認された、又は既に上市された製品が法的措置を受け、場合によっては市場から撤回される可能性があることから、市場における不確実性を生み出すリスクがある。専門委員の意見の結果に関わらず、この制度は特許紛争に対する法的拘束力のある解決を提供するものではない。この制度により、このような「リスク付き」の後発医薬品の上市が増加すれば、特許権者が専門委員の判断に異議を唱えるために裁判所に訴えることになり、訴訟の数が増加する可能性がある。また、特許権者は法的手段が制限されるおそれがあることから、機密情報の開示を求められるプロセスに協力する可能性は低い。
さらに、PhRMAは、厚労省が専門委員制度を設けることによって生じる可能性のある法的・政策的課題とは別に、草案では、この制度がどのように運営されるかについて、以下のように多くの疑問を提起しています。
- 最終的なパテントリンケージの判断は厚労省が行うとされているが、提案されている制度がより複雑な事案を対象としていることを踏まえると、実際にはほとんどの場合において厚労省が専門委員会の判断に依拠する可能性が高くなるのではないか。
- 専門委員会の委員の身元が非公開であり、関係当事者がその委員の参加に異議を申し立てる仕組みがない中で、厚労省はどのようにして専門委員の中立性を担保するのか。専門委員会の候補となる弁護士の多くが一般的に先発企業またはジェネリック企業のいずれかを代表しており、利益相反の可能性があると考えられる。
- 厚労省は、専門委員会および省内の審査官が裁判所や特許庁における最新の判例を把握することをどのように担保するのか。
- 専門委員会の判断は全会一致である必要があるのか。そうでない場合、厚労省は相反する専門委員会の意見の間でどのように判断をするのか。
- 運用指針では、専門委員会が、先発医薬品の製造販売業者または特許権者の意見、および後発医薬品申請者の意見を考慮するとされている。しかし、当該指針には、当事者の意見がどのように考慮されるのか、あるいは当事者が互いの意見や専門委員会の予備的な判断に対して反論する機会があるのかについて、一切の詳細およびタイムラインが記載されていない。
- 後発医薬品およびバイオ後続品に関連するすべての関連特許(製剤特許や製法特許を含む)が専門委員会の審査対象となることを、厚労省が確認することができるのか。裁判所が考慮しうるすべての関連特許を考慮しなければ、専門委員会が後発医薬品やバイオ後続品申請に関する侵害リスクを正確に判断することは困難といえる。

「草案」の内容は公開されていませんが、この意見書を読むと、かなり多くの欠陥がありそう・・・。「運用指針」って、制度の骨格(法制)が不在なまま、付け焼き刃的にさらに「運用」で整えるつもりなのでしょうか・・・
2.PhRMAの提言
PhRMAは、制度の本質的な欠陥として、「特許権者への事前通知」が制度設計に含まれていない点を重ねて批判しています。専門委員会との協議が発生するか否かは審査側の判断次第であり、結果として特許権者が無通知のまま後発申請の存在を知らない可能性が残るという構造的な問題を指摘しています。
具体的には、以下の対応が不可欠であると提案しています。
- 後発医薬品・バイオ後続品の申請時点で、かつ承認前に、必ず特許権者へ通知を行う制度を導入すべきである。
- 特許紛争が生じた場合には、解決まで当該後発品を薬価基準に収載しない措置を講じるべきである。
- このような制度改正は、迅速な後発品承認と特許権者の保護を両立しつつ、供給の混乱や市場の混迷を最小限に抑えると考える。
- また、透明性の向上に資することに加え、裁判所による「確認判決が得られない」旨の判決に伴う懸念を一部解消する可能性がある(最終的には、この問題は日本のパテントリンケージ制度の見直しではなく、司法制度の改革によって対処されるべきである)。
3.考察
PhRMAは、2025年4月29日に公表されたスペシャル301条報告書(Special 301 report)に向けて提出された意見書の中でも、日本のパテントリンケージ制度に関する問題点を指摘しています。
参照:

PhRMAの主張は一貫しており、日本のパテントリンケージ制度が「特許権者への事前通知」制度を欠く点に問題の本質があるとの立場です。実際、米国のHatch-Waxman制度における「Paragraph IV通知」との対比において、日本の制度は特許権侵害訴訟の開始時点が遅れやすく、予測可能性に乏しい構造を持っていることは否定できません。
専門委員会の制度については、厚労省として「行政判断の限界」を認識したうえで、その制度が裁判所による紛争解決に代替するものではない以上、実効性に疑問が残るのも事実です。
さらに、委員の中立性や透明性、判断対象特許の範囲といった運用設計についても、制度導入に際しては丁寧な議論と適切な法制化が不可欠です。「草案」がどのようなものかは公に明らかになっていませんが、少なくとも現状の設計案だけで制度化するには、実務的・法的なリスクを孕んでいるように感じられます。
最後に、PhRMAが求めている通知制度の導入については、透明性・予見可能性・訴訟回避の観点から、日本でも一定の議論の余地があります。厚労省の立場からは、申請者への負担や審査のスピード感への影響を考慮して消極的になりやすい論点ですが、製薬業界全体の信頼性確保という観点から、慎重かつ開かれた議論の場が今後必要とされると考えられます。
参考:
パテントリンケージ制度に関連した事件や制度の課題を指摘した以下の記事もぜひご覧ください。

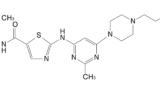
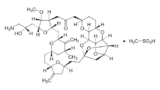


音声で、ゆるっと解説。ぜひお聴きになってみてくださいませ。
特許的ブログ ON AIR! 〜医薬×知財を、ゆるっと解説♪〜
※ 当解説の情報はその正確性と現在の適用可能性を再確認する必要があります。
アシスタントたち:

Robot icons created by Freepik – Flaticon; Robot cat icons created by Freepik – Flaticon


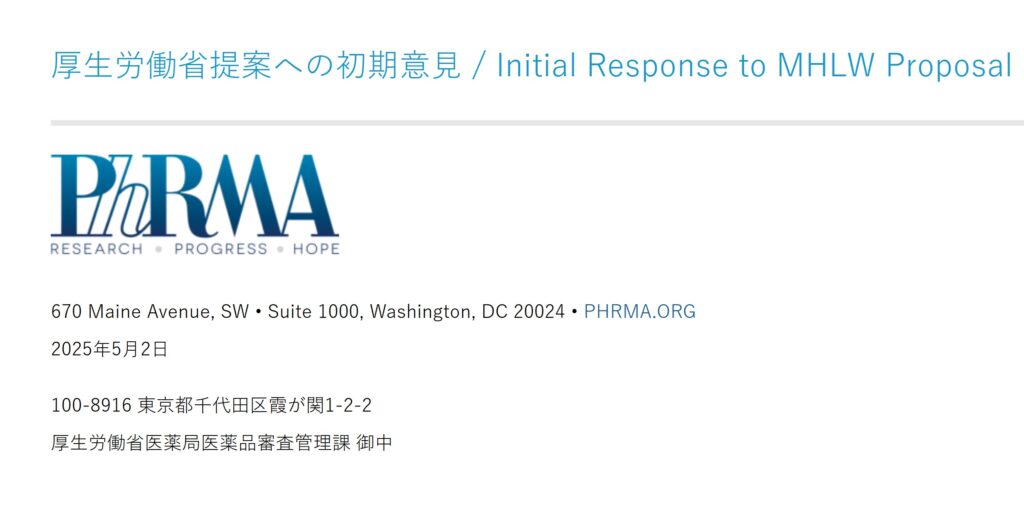

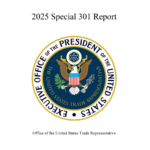
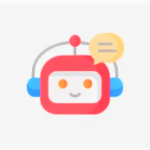
コメント