厚生労働省は、これまで後発医薬品の承認審査において、平成21年の「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」(平成21年6月5日付け医政経発第0605001号、薬食審査発第0605014号医政局経済課長、医薬食品局審査管理課長連名通知。以下「二課長通知」)に基づき、先発医薬品の特許(物質特許・用途特許)と後発医薬品との関係を確認してきました。
この運用は、医薬品の安定供給を確保する観点から、いわゆるパテントリンケージ制度として定着しています。
参照:
- 2009.06.11ブログ記事「2009.06.05 「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」」
■ 新たな通知の発出
2025年10月8日、厚生労働省はこの平成21年の二課長通知を改正し、新たな通知「医療用後発医薬品及びバイオ後続品に関する医薬品医療機器等法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」(令和7年10月8日付け医政産情企発1008第1号・医薬薬審発1008第5号、医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、医薬局医薬品審査管理課長 連名通知)を発出しました。
参照:
- 医療用後発医薬品及びバイオ後続品に関する医薬品医療機器等法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて(令和7年10月8日付け医政産情企発1008第1号、医薬薬審発1008第5号、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、医薬局医薬品審査管理課長 連名通知)
- 2025年10月8日掲載 厚生労働省: 医薬品特許情報
■ 改正の背景とポイント
これまでバイオ後続品については、平成21年の二課長通知に「準じて」扱われてきましたが、正式に対象として明記された通知は存在しませんでした。
今回の改正により、バイオ後続品も正式にパテントリンケージ制度の対象として明記される形となりました。
この動きは、2024年7月25日の厚生科学審議会(医薬品医療機器制度部会)で議論された「後発医薬品等の承認審査におけるパテントリンケージ制度の運用改善」に端を発します。同部会では、医薬品特許の専門家への意見照会制度の導入など、より透明性・客観性の高い運用への改善を検討することが了承されました。
参照:

■ 医薬品特許情報報告票の提出
新たな通知では、特許権者又は先発企業は、後発医薬品等の承認審査において考慮を求める物質特許又は用途特許がある場合、先発医薬品の再審査の調査期間終了前に、医薬品特許情報報告票を厚生労働省医薬局医薬品審査管理課に提出する義務があり、報告されない特許は、原則として考慮されないことが明確化されました。
また、再審査の調査期間の終了後、新たに物質特許又は用途特許が登録された場合には、特許公報発行日から30日以内に報告票を提出する必要があります。
■ 承認判断の原則の明確化
新通知においても、次の原則が再確認されています。
(1)先発医薬品(先行バイオ医薬品を含み、体外診断用医薬品を除く。以下同じ。)の有効成分に特許(物質特許)が存在することによって、当該有効成分に係る医薬品の製造又は製造販売ができない場合には、後発医薬品等を承認しない。
(2)先発医薬品の一部の効能又は効果、用法及び用量(以下「効能効果等」という。)に特許(用途特許)が存在する場合であっても、その他の効能効果等を標ぼうする医薬品の製造又は製造販売が可能である場合については、後発医薬品等を承認できることとする。この場合、特許が存在する効能効果等については承認しない。
この点は、制度の根幹に関わる基本方針として明確に位置づけられています。
厚生労働科学特別研究事業として2025年6月に公開された「日本型パテントリンケージ制度において医薬品特許の専門家の意見を反映させる仕組みの構築に向けた調査研究」の総括報告書では、「物質特許」及び「用途特許」の定義・範囲に関して看過できな問題点がありました(2025.07.02ブログ記事「日本型パテントリンケージ制度において医薬品特許の専門家の意見を反映させる仕組みの構築に向けた調査研究」参照)。しかし、今回の通知では、これらの再定義や範囲変更は行われず、従来の運用が維持された形です。このことから、厚労省は調査研究結果を踏まえつつも、関係業界等の意見を総合的に勘案して慎重な判断を行ったものと考えられます。

調査研究の報告書はあくまで調査研究者の意見。それを参考にしつつも業界等の意見も踏まえて厚労省が検討・判断したのでしょう。まだまだパテントリンケージ制度に関する調査研究は続くようですので、今後の検討を期待しています。
■ 本通知の内容
本通知の内容は以下のとおりです((別紙)医薬品特許情報報告票は省略)。
医療用後発医薬品及びバイオ後続品に関する医薬品医療機器等法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて
医療用後発医薬品に関する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについては、「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」(平成21年6月5日付け医政経発第 0605001号、薬食審査発第0605014号医政局経済課長、医薬食品局審査管理課長連名通知。以下「二課長通知」という。)にて示したとおり、医薬品の安定供給を図る観点から、承認審査の中で、先発医薬品と医療用後発医薬品との特許抵触の有無について確認を行うよう求めているところです。
また、特許に関する懸念がある医療用後発医薬品の薬価収載に当たっては、事前に当事者間で調整を行い、安定供給が可能と思われる品目についてのみ収載手続をとるよう求めているところです。
一方、バイオ後続品(国内で既に製造販売承認を与えられているバイオテクノロジー応用医薬品(以下「先行バイオ医薬品」という。)と同等/同質の医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品をいう。以下同じ。)に関する医薬品医療機器等法上の承認審査及び薬価収載における医薬品特許の取扱いについては、従来、二課長通知に準じ、医療用後発医薬品と同様の運用をしてきたところです。
今般、医療用後発医薬品及びバイオ後続品(以下、併せて「後発医薬品等」という。)に係る医薬品特許の取扱いについて、下記のとおり明確化することとしましたので、貴管内関係事業者に対して周知方よろしくお願いいたします。
なお、二課長通知、「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて」(平成6年10月4日付け薬審第 762 号厚生省薬務局審査課長通知)、「医薬品製造(輸入)承認申請時に添付する特許情報について」(平成7年2月9日付け厚生省薬務局審査課事務連絡)及び「特許期間と後発品の申請時期について」(平成7年6月28日付け厚生省薬務局審査課事務連絡)については、本通知発出日をもって廃止することとします。
記
1.承認審査に係る医薬品特許の取扱いについて
後発医薬品等に関する医薬品医療機器等法上の承認審査に当たっては次のとおり取り扱うこととする。なお、以下について、特許の存否は承認予定日で判断するが、特許期間の終了を見込み、承認審査の標準的事務処理期間を考慮して後発医薬品等の承認申請を行うことは差し支えないものとする。
(1)先発医薬品(先行バイオ医薬品を含み、体外診断用医薬品を除く。以下同じ。)の有効成分に特許(物質特許)が存在することによって、当該有効成分に係る医薬品の製造又は製造販売ができない場合には、後発医薬品等を承認しない。
(2)先発医薬品の一部の効能又は効果、用法及び用量(以下「効能効果等」という。)に特許(用途特許)が存在する場合であっても、その他の効能効果等を標ぼうする医薬品の製造又は製造販売が可能である場合については、後発医薬品等を承認できることとする。この場合、特許が存在する効能効果等については承認しない。
2.特許状況に関する資料の提出について
(1)後発医薬品等の製造販売承認申請を行う者は、上記1.の取扱いを考慮し、先発医薬品の有効成分に係る物質特許及び用途特許の有無並びにこれらの特許に係る情報について、事前に十分に確認を行うこと。また、製造販売承認の取得後速やかに製造販売できることを示す資料を、製造販売承認申請書の添付資料(例えば、CTD1.4「特許状況」の添付資料)として、又は厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの求めに応じて提出すること。
(2)2.(1)の「製造販売承認の取得後速やかに製造販売できることを示す資料」とは、例えば、以下が該当する。
(ア)特許権が消滅していることを示す場合
閉鎖特許原簿、特許内容(特許番号、特許権者名、特許期間等)等
(イ)特許が無効であることを示す場合
特許無効審決書、裁判判決文等(※)
(ウ)特許権を侵害しないことを示す場合
裁判判決文等(※)
(エ)特許権者又は専用実施権者の同意を得ていることを示す場合
契約書(写)、同意書等(※)
※特許内容(特許番号、特許権者名、特許期間等)を参考資料として添付すること。
なお、当該申請に係る後発医薬品等とその先発医薬品との特許抵触の有無に関する申請者の見解を記載した資料を上記の資料と併せて提出することも差し支えない。3.薬価収載手続に係る医薬品特許の取扱いについて
特許係争のおそれがあると思われる品目の薬価収載を希望する場合は、事前に特許権者又は実施権者である先発医薬品の製造販売業者(以下「先発企業」という。)との間で調整を行い、将来も含めて医薬品の安定供給が可能と思われる品目についてのみ収載手続をとること。
4.医薬品特許情報の収集について
特許権者又は先発企業は、後発医薬品等の承認審査に当たって考慮されるべきと考える先発医薬品の有効成分に係る物質特許又は用途特許(いずれも延長された特許を含む。以下同じ。)が存在する場合には、先発医薬品の再審査の調査期間終了前に、別紙の医薬品特許情報報告票に必要事項を記入し、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課宛てに提出すること。
また、当該調査期間の終了後、新たに物質特許又は用途特許を登録したときは、特許公報発行日から30日以内に別紙の医薬品特許情報報告票に必要事項を記入し、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課宛てに提出すること。
医薬品特許情報報告票により報告されない先発医薬品の有効成分に係る物質特許又は用途特許については、原則として、後発医薬品等の承認審査に当たって考慮しないが、「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて」(平成6年10月4日付け薬審第762号厚生省薬務局審査課長通知)に従い、既に独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出されたものについては、改めて厚生労働省に提出することは不要とする。また、本通知発出日時点において既に再審査の調査期間が満了している先発医薬品について、未だ医薬品特許情報報告票を提出していなかったものの、後発医薬品等の承認審査に当たって考慮されるべきと考える特許が存在する場合には、令和7年11月8日までに、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課宛てに提出すること。
なお、医薬品特許情報報告票については一般には公開しないこととする。
■ 今後の展開
バイオ後続品を正式に対象に含める今回の新通知の発出と並行して、パテントリンケージ制度の運用改善に向けた「専門家意見照会制度」の導入を厚生労働省は検討しており、その導入開始も間近とみられています。様々な課題が山積の日本のパテントリンケージ制度ですが、この照会制度導入が大きな一歩となるのでしょうか。
参考:
- 「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)(平成21年6月5日付医政経発第0605001号/薬食審査発第0605014号)」及び「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて(平成6年10月4日付け薬審第762号審査課長通知)」
- 2009.06.11ブログ記事「2009.06.05 「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」」
- 2021.03.08ブログ記事「日本のパテントリンケージの現状の課題とその解決に向けた提案」
- 2023.09.18ブログ記事(2023.10.31更新)「【アンケート】パテントリンケージとして運用されている二課長通知の問題点は何だと思いますか?」
- 2024.07.25ブログ記事「【速報】厚生科学審議会(医薬品医療機器制度部会) パテントリンケージ制度の運用改善について議論 医薬品特許の専門家への意見照会制度の導入検討へ」
- 2025.05.03ブログ記事「【速報】PhRMA、厚労省提案のパテントリンケージ制度に懸念を表明」
- 2025.07.02ブログ記事「日本型パテントリンケージ制度において医薬品特許の専門家の意見を反映させる仕組みの構築に向けた調査研究」
- 医療用後発医薬品及びバイオ後続品に関する医薬品医療機器等法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて(令和7年10月8日付け医政産情企発1008第1号、医薬薬審発1008第5号、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、医薬局医薬品審査管理課長 連名通知)
- 2025年10月8日掲載 厚生労働省: 医薬品特許情報



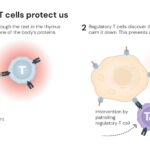

コメント